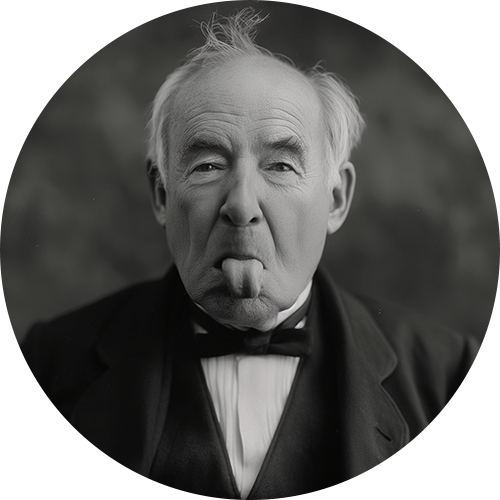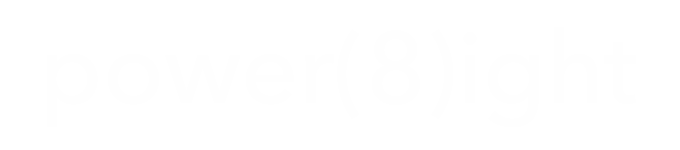プロボノ(Pro Bono)とは?—無償と有償の境界線と世界の潮流

「プロボノ(Pro Bono)」という言葉は、最近ではビジネスパーソンの間でもよく耳にするようになってきました。日本では「ボランティア」と言うと、無償で行う善意の活動というイメージが強いですが、世界ではもう少し多様で柔軟な考え方が存在します。本記事では、プロボノの定義と国内外における無償・有償ボランティアの考え方、そして現場で起こりうるトラブルなどについて解説します。
1. ボランティアとその形態:無償と有償の違い
日本におけるボランティア活動は、基本的に「無償」であることが前提とされがちです。災害支援や地域清掃など、多くの活動が自発的かつ報酬なしで行われています。しかし、世界を見渡すと、交通費や食費、時間的な対価などを支払う「有償ボランティア」も一般的です。
無償ボランティアの特徴:
- 完全な善意による参加
- 交通費や物資など自己負担が多い
- 一定の時間やスキルを提供
有償ボランティアの特徴:
- 一部費用や報酬が支払われる
- 責任やスキルが求められる場合も
- 職業とボランティアの中間的な位置づけ
日本では「お金をもらったらボランティアじゃない」と考える風潮もありますが、欧米諸国ではむしろ「持続可能性を担保するための報酬」として、有償での支援も広く受け入れられています。
2. プロボノとは何か?
「プロボノ(Pro Bono)」とは、**“Pro Bono Publico”(公共善のために)**の略で、主に専門職のスキルを活かして社会貢献を行う活動のことを指します。弁護士や会計士、ITエンジニア、デザイナーなどが、自らの専門性を無償で提供する形態が代表的です。
プロボノの特徴:
- 専門的スキルに基づく支援
- 一般的には無償(ただし実費精算があることも)
- 社会課題解決に焦点
- 継続的な支援を前提にするケースもある
3. 世界におけるプロボノの広がり
プロボノはアメリカで始まり、特に弁護士業界での活動が知られています。米国では、法律事務所が年間に一定時間をプロボノに割くことが推奨・義務化されているケースもあります。
欧州やアジア、南米でもプロボノ文化は拡大中で、企業単位での取り組み(企業プロボノ)や、オンラインマッチングプラットフォームを通じた参加なども活発になっています。
- アメリカ: 弁護士に年間50時間のプロボノを推奨(ABA)
- 韓国: 公的支援機関がプロボノをコーディネート
- ドイツ: 社会的企業との連携事例が多数
4. どこまでがボランティアなのか?
「交通費をもらったらボランティアじゃない?」「専門職の提供は仕事では?」という疑問もよく聞かれます。ここで重要なのは、「動機」と「目的」です。
- 無償=ボランティアではなく、自己利益よりも公共性を重視するかどうかがポイント。
- 有償であっても、営利目的でなければボランティア的と捉える国もあります。
ボランティアと仕事の境界は、もはや線引きではなくグラデーションになっているのが現実です。
5. プロボノで起こりうるトラブル
プロボノは善意で行われるものですが、以下のようなトラブルが発生することもあります。
- 責任の所在が不明確:納期や品質が曖昧なまま進行すると、期待とのギャップが生まれる。
- 依頼側との温度差:「タダだから文句は言えない」という誤解、逆に「無料なんだから何でもしてくれるでしょ?」という依頼側の過剰期待。
- スキルミスマッチ:実際のニーズと提供されるスキルが合っていない。
- 継続性の欠如:短期で終わってしまい、成果が定着しない。
トラブルを防ぐには、事前の合意形成やマッチング精度、双方の信頼関係が大切です。

6. これからのボランティアとプロボノ
持続可能な社会を目指すうえで、ボランティアも多様な形があってよい時代です。プロボノのような「専門性の寄付」は、単なる善意にとどまらず、社会の仕組みに変化をもたらす可能性を秘めています。
- 企業活動の一環としてのプロボノ(CSR)
- 若手のキャリア形成としての参加
- 自治体やNPOとの協働モデル
無償か有償かではなく、「どのような価値を社会にもたらすか」が、これからのボランティアやプロボノの評価軸になっていくでしょう。
あなたは、どんな形で社会に関わりたいですか?プロボノという選択肢を、今こそ身近なものとして考えてみてはいかがでしょうか。